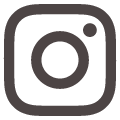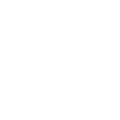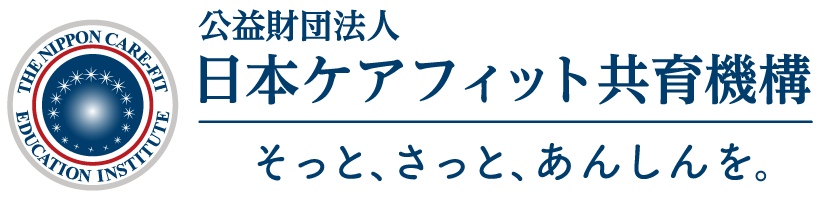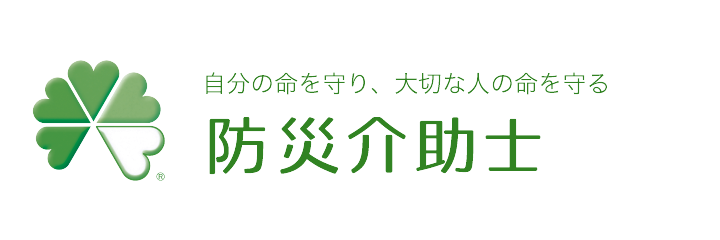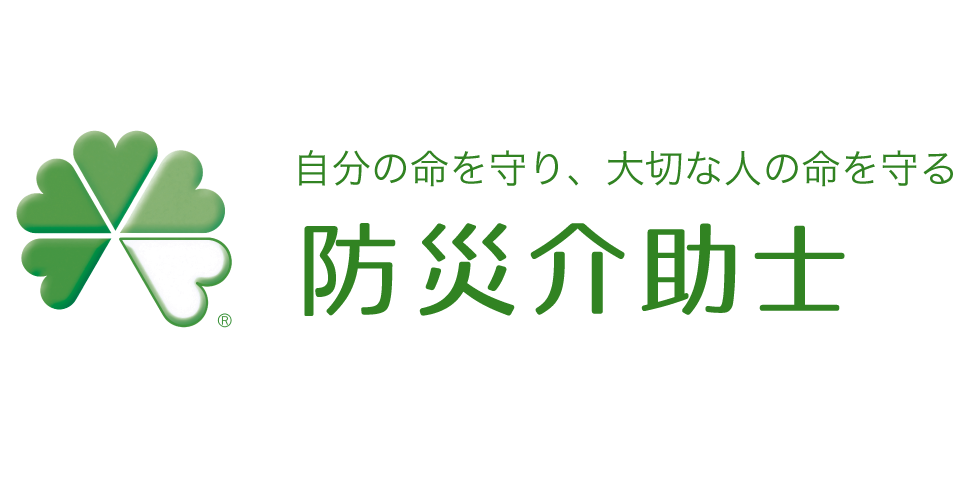
インクルーシブ防災とは?-「誰も取り残さない」防災について考える-
掲載日:
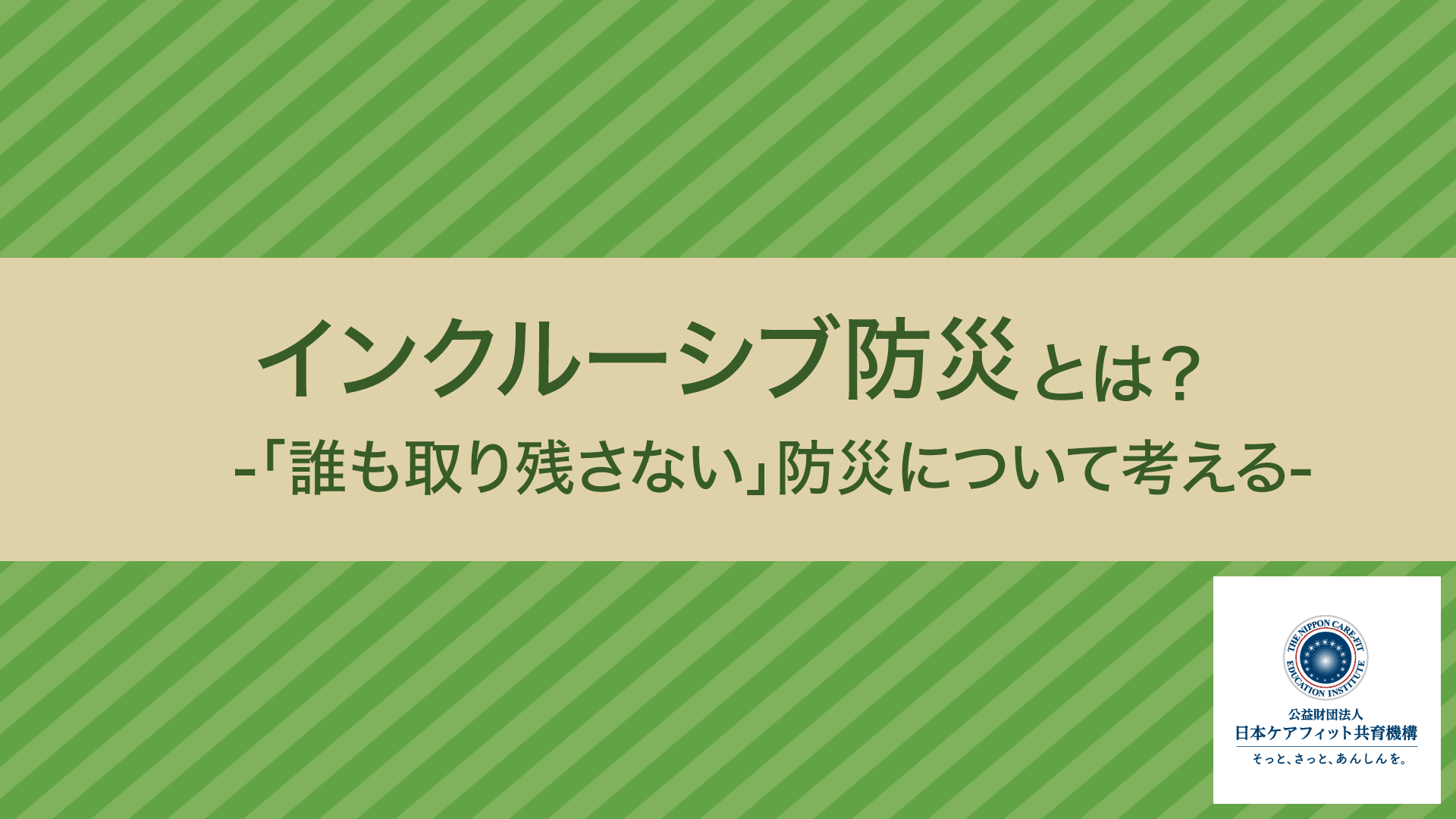
「インクルーシブ防災」という言葉を知っていますか?
インクルーシブ防災とは簡単に言うと、障害者や高齢者を含む、あらゆる人を取り残さない防災という考え方です。
過去の災害でも、障害者や高齢者が取り残されて亡くなるケースが多くあります。
SDGsが広まる背景で「誰も取り残さない」やダイバーシティ(多様性)という言葉がいたるところで見られるようになった現代では、災害時でも多様な人を想定する考え方が大切になっています。
本記事では、そのような防災と人の多様性について、「インクルーシブ防災」をキーワードに考えます。
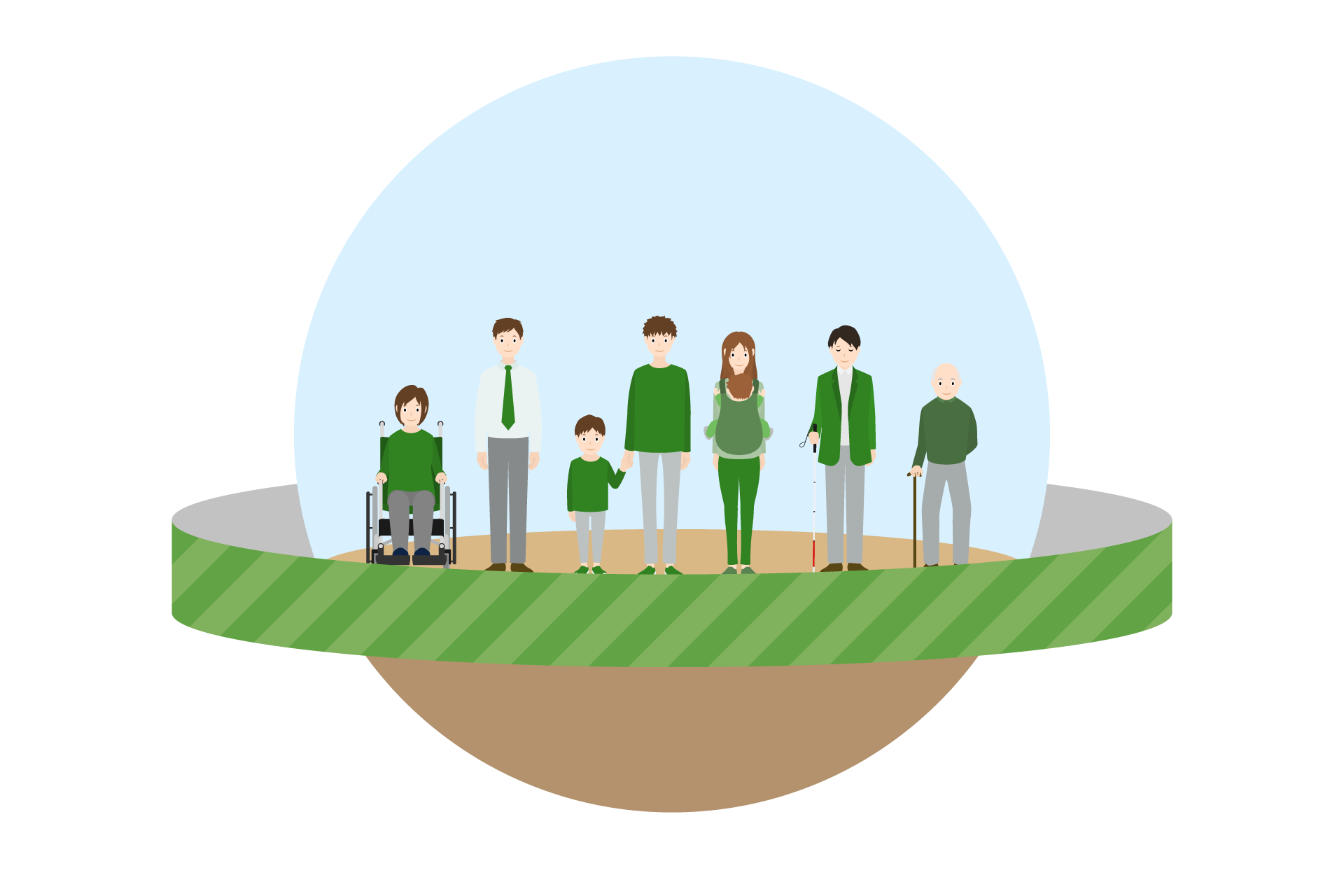
インクルーシブ防災の広がり
インクルーシブ防災が広まるきっかけとなったのは、2015年の3月14日から18日まで、宮城県仙台市で開催された第3回国連防災世界会議です。
国連防災世界会議とは、全世界の災害による被害の軽減を目指す、世界の防災指針を策定する国連主催の会議です。
延べ15万人以上が参加したとされる第3回会議で「仙台防災枠組2015-2030」外部サイトが採択され、今後の防災における指針が示されました。
この会議で、「障害者と防災」というテーマが大きく取り上げられ、インクルーシブ防災につながっていきます。
データから見る「誰も取り残さない」ことの重要性
日本は災害大国であり、事実、過去の国連防災世界会議はすべて日本で行われています。(1994年横浜 2005年神戸 2015年仙台)
過去の2開催でも防災における様々な話し合いが行われましたが、障害者などの要配慮者に関する議論はほとんど行われませんでした。
しかし、2011年に日本史上類をみない大災害である、東日本大震災が起こり、要配慮者の被害の大きさが浮き彫りになりました。
過去のリベルケアフィットでも言及していますが、東北3県の人口2401955人のうち18829人が亡くなっており、東北3県での人口の死亡率が0.78%であるのに対し、障害者(障害者手帳所有者)は人口115859人のうち1658人が亡くなり、死亡率は1.43%です。
つまり、東日本大震災における障害者の死亡率は一般的な死亡率の約2倍となっています。
さらに、避難生活等の身体的負担による疾病等、災害に関連した原因でなくなる災害関連死を見ても、東日本大震災の災害関連死における障害者の割合は24.6%となっています。
関連記事:災害関連死 高齢者・障害者が多い原因は?東日本大震災と熊本地震の事例から考える
このような数値には、防災を考える現場に障害当事者の意見が反映されていないという現状も関係しています。
例えば、先ほどの国連防災世界会議では、第3回で「障害と防災」が取り上げられるまでは、障害者が実際に意見を述べる機会が限られていました。
このような事態を防ぐためには、障害者、高齢者、健常者など、世の中には多様な人が存在し、その人それぞれに適切な防災の方法があることを認識する必要があります。
では、実際にはどのような取り組みがされているのでしょうか?
具体的な取り組みの紹介
大分県別府市「別府モデル」
こここでは、インクルーシブ防災の考え方を取り入れた事業モデルとして、大分県別府市で確立された「別府モデル」を紹介します。
このモデルの特徴としては、以下のような事柄が挙げられます。
- 福祉事業所職員の支援を受けながら障害者や家族が自らの避難計画を作る
- 自治会と調整会議を開き、地域の実情を計画に反映させる
- 地域の防災訓練で実践・検証する
参考:「別府市におけるインクルーシブ防災事業」について外部サイト
ここでのポイントは、このモデルが障害者と住民の交流が深まる仕組みであったことです。
特に災害時では、障害者や高齢者などの要配慮者の支援は地域ぐるみでの支援体制がなくては成り立ちません。
要配慮者はどこに、何人いるのか。
災害時にその人たちはどのように避難するのか。
その情報はどのように共有されるのか。
緊急時に誰も取り残さないよう行動するためには個人と地域、両方の防災意識が必要不可欠です。
インクルーシブ防災と
防災介助士
防災介助士では、災害とは何か、を学び、高齢者や障害者など、災害時に配慮を必要とする、避難行動要支援者への応対について学ぶことができます。 防災においても忘れがちな多様な人への対応、バリアフリー対応についてしっかり備えておきましょう。
リベル・ケアフィット 〜「気づき」が集う場所〜
-
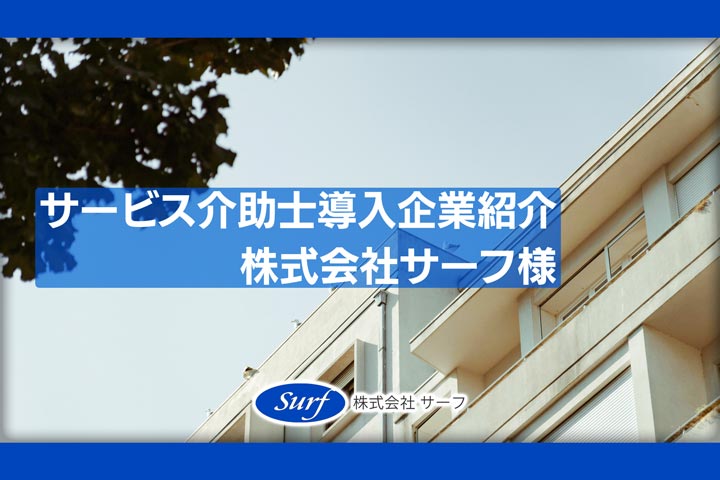
サービス介助士導入企業紹介:株式会社サーフ様
掲載日:
10年以上にわたってサービス介助士の資格取得を継続いただいている株式会社サーフ様。マンション等の大規模修繕事業を展開される同社が、なぜサービス介助士の資格取得を重視されているのか。古川文仁社長にお話を伺いました。
-

「人にしかできないサービス」を追求する——紀ノ國屋が取り組むホスピタリティ
掲載日:
「食を豊かに、人生を豊かに」という理念を掲げる株式会社紀ノ國屋様。1953年には日本初のセルフサービス方式スーパーを開業するなど、流通・小売りの革新を重ねてきました。その長い歴史の中で多くのファンを獲得し、誰もが安心して買い物ができる空間づくりを目指してサービス介助士の資格取得を推進いただいています。紀ノ国屋様のお取り組みについて、インタビューさせていただき、記事にさせていただきました。
-

日本の高齢者人口3,619万人! - 超高齢社会と認知症の推移(2025年版) -
掲載日:
毎年敬老の日に合わせて総務省統計局から発表される日本の高齢者人口。令和7年9月15日付の総務省からの発表によると2025年9月現在の高齢者人口は3,619万人、高齢者人口率は29.4%となりました。超高齢社会が進むと切り離すことのできないテーマが認知症です。これからも社会の高齢化が進行するとどのようなことが起こりえるのか、高齢者に関する様々なデータを見ながら考えていきましょう。