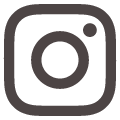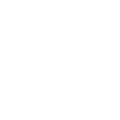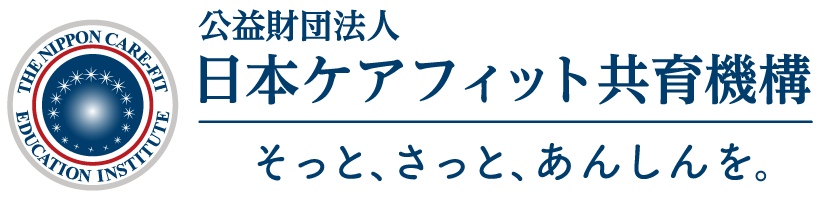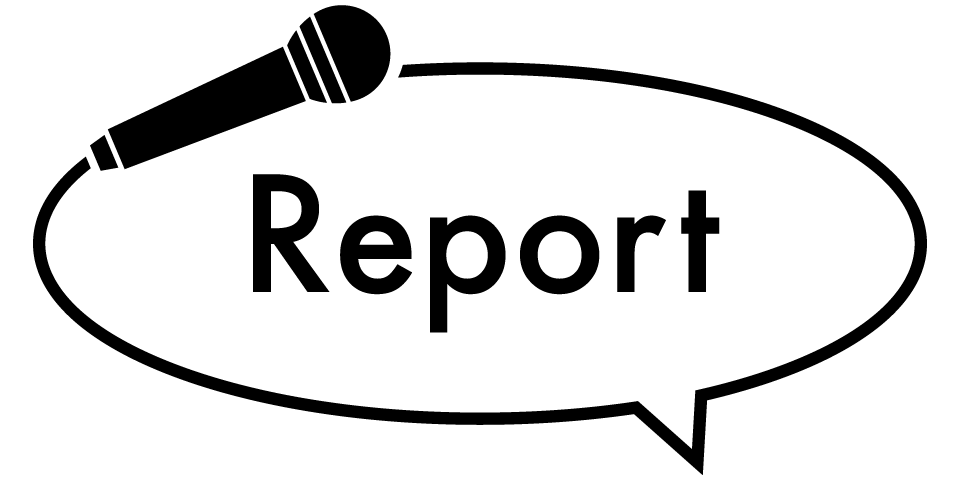
音のない世界で新たな自分と出会う「ダイアログ・イン・サイレンス」
掲載日:

皆さんは「ダイアログ」の意味をご存知でしょうか?
日本語に訳すと「対話」です。
もしあなた自身が「音のない世界」にいたとしたら、家族や友人、周りにいるさまざまな人たちとどのように対話するでしょうか。
聞こえない世界での対話について考え、知り、その楽しさを感じることができる「ダイアログ・イン・サイレンス」。昨年から日本でも期間限定で開催され、約1万人が体験したイベントです。
ダイアログ・イン・サイレンスは1998年にドイツで生まれ、これまでに世界で100万人以上が体験しています。
今回は、今夏開催されたダイアログ・イン・サイレンスの体験レポートをお届けします。
皆さんも「音のない世界」に飛び込んだ気持ちで読んでみてください。
ようこそ静寂の世界へ

この体験プログラムでは、12人の仲間と一緒に、音を遮断するヘッドセットをつけて声を発さないことから始まります。私たちの前を歩き、誘導してくれるのは、この世界の案内をしてくれる素敵なアテンド。アテンドの方々はみな聴覚に障害があります。
今回のアテンド、あちゃこ※が口に人差し指をあて「しーっ」と合図をします。
私たちのいる場所は、一瞬にして静寂の世界へと切り替わりました。
「聞こえないこと」が当たり前の世界に入ると、どうしたらよいか分からず戸惑いましたが、彼女の豊かな表情と身振り手振りによって、徐々にわくわくとした気持ちが沸き起こってきました。
さあ、どんなことが待っているのでしょうか。
※アテンドの方々はニックネームで呼びます。
手で、顔で。心躍るコミュニケーション
部屋を進みながら手を使ったり、表情を真似したり。
音のない世界でのコミュニケーション方法が増えていきます。

暗闇の中に、光る台がひとつ。全員で輪になって手できつねの形をつくり、交差させて隣の人とコミュニケーションを取ってみました。この光景は、まるで影絵劇のように幻想的で、言葉がなくても初対面の人との距離が縮まり、全員がひとつになった瞬間でした。

額縁の前に1人ずつ立ち、画面に映し出された表情の写真を見て、同じ表情をします。同じ笑顔でも、にっこりと歯を見せる人、くしゃくしゃと目がなくなるほどに笑う人、ひとりひとりの個性が光ります。音のない世界において、自分の気持ちをしっかりと表情に出すこと、これも欠かせないコミュニケーション方法なのです。

普段人の目を見て話すことが苦手ですが、音のない世界ではただただ目を見て、表情を見て、相手の気持ちを感じ取る。それだけでとても安心していることに気づきました。
新しい対話のカタチ
聴覚に障がいのある方とのコミュニケーション方法として、手話や筆談などが知られています。しかしながら、障害の有無にかかわらず、地域や言語の違いによっては即座にコミュニケーションを取ることが難しい場面に遭遇した経験がある方も多いと思います。
そんなとき、言葉に頼らないコミュニケーションをするとしたら…どんな方法があるでしょうか。ぜひ想像してみてください。
ダイアログ・イン・サイレンスは、固定概念に縛られず、楽しみながら新しい自分を発見できた、ちょっとした旅のような時間でした。
2019年の夏にも開催を予定しています。
ダイアログ・イン・サイレンスのプログラム内でも、全員で一緒に手話を使い、表現する時間があります。
日本ケアフィット共育機構では、サービス介助士での学びだけでなく、ろう者をゲストに招いた手話カフェも毎月開催しています。静寂の世界での手話を一緒に楽しみましょう。
ちょこっと手話カフェ
リベル・ケアフィット 〜「気づき」が集う場所〜
-

サービス介助基礎研修 導入企業紹介(株式会社マイヤ様)
掲載日:
1961年に岩手県大船渡市にて創業されて以来、地域の暮らしに必要不可欠な存在として地域の皆様の健康で豊かな食生活に寄与されている株式会社マイヤ様。
株式会社マイヤ様で2023年より実施させていただいているサービス介助基礎研修について、今年度もマイヤびはんストアオール店、マイヤ赤崎店、マイヤマスト店にて実施をさせていただきました。 -

サービス介助士資格導入企業紹介:株式会社ムジコ・クリエイト様
掲載日:
自動車教習所や各種講習の現場には、年齢や身体状況、経験の違いによって、さまざまな不安や困りごとを抱えたお客様が訪れます。安全に学べる環境を整えることはもちろん、その前提として「安心してその場にいられること」をどう支えていくのか──。今回お話を伺ったのは、株式会社ムジコ・クリエイト様。モータースクール事業に携わる松原様、蝦名様にお話をうかがい、サービス介助士資格を導入した背景や、現場で感じている変化について語っていただきました。
-

【バリアフルレストラン実施事例】株式会社INPEX様
掲載日:
日本ケアフィット共育機構が提供する「バリアフルレストラン」は、“障害の社会モデル”の考えに基づいて、社会の多数派と少数派の立場を“反転”させた世界を体験することで、無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)や社会のつくりに潜む“バリア”を理解する体験型プログラムです。