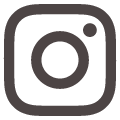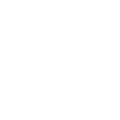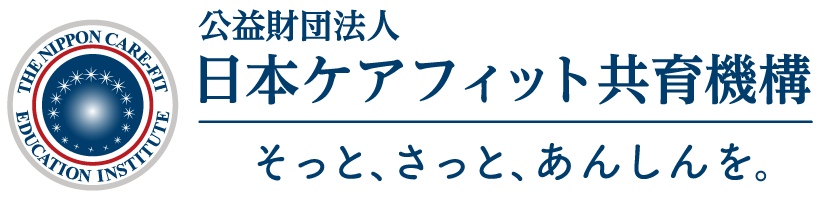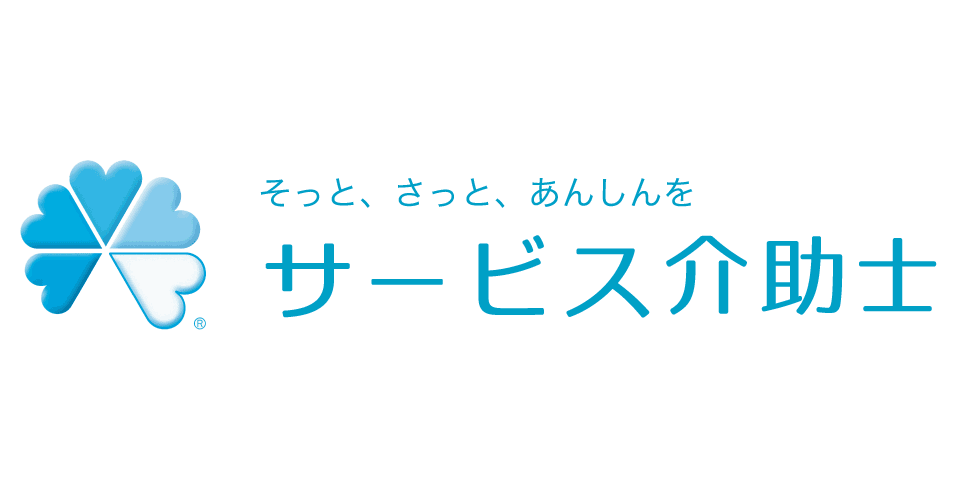
障害のある人も楽しめるバリアフリーな映画館
日本で唯一のユニバーサルシアター CINEMA Chupki TABATA【後編】
掲載日:

今回はバリアフリーの映画館レポート後編です。
設立への想い、実際に利用をされたお客さまからの声、また2020年へ向けて今の社会の現状や今後の抱負や目標を「バリアフリー映画鑑賞推進団体City Lights」代表、平塚 千穂子さんにお話いただきました。
- お客さまから言われて嬉しかったことはなんですか
平塚さん障害の有無にかかわらず、「くつろげるスペースですね」「いい映画館ですね」とおっしゃっていただけたこと、安心できるとか安らげるといった声を多くいただいていることです。
私たちは映画館を設立するときに、普段日常生活では色んな情報が入ってくる、だけどここではそれを忘れられるような場所にしたいと思い設立しました。ですので映画館では予告編の上映もしていないんですよね。
またシアターは森の中をイメージしているので、緑のものや木のテイストにしていたり、くまのぬいぐるみや鳥の巣があったり、アロマも檜の香りにしたり、Chupki (自然界の光)ですから自然を感じられる空間にしたいと思っていて、予告編がない代わりに、「森の一日を音で表現する」をコンセプトに世界的に有名な音楽監督の岩浪美和さんに音を作っていただき、朝は小鳥が鳴いて日が昇って、夕方になると蛙が鳴いて、夜になると鈴虫が鳴いて、映像でも1日の移り変わりを表現して繰り返し流しています。
お客さまの中には長く滞在される方もいらっしゃって、週末ここでくつろぐために地方からお越しになる方もいます。朝からいて、1日中映画を楽しんで帰るというのを習慣にされている方もいるんですよ。
そのような安心しゆっくりできる場所を作りたかったので、とても嬉しかったです。

- 今の社会の現状を見て課題はありますか
平塚さん街の中のコミュニティスペース、映画館もそういう場所だと思いますが、そういった場所に様々な障害のある方を受け入れる体制が整っている場所があるだけで、街が変わってくるなと感じています。
例えば、視覚に障害のある方でも「Chupkiに通いたいから一人で頑張って行ってみる」という方もいらっしゃいます。ただ道に迷う方もいらっしゃいます。でも街の人が声をかけて連れてきてくれる、映画を2、3本はしごして見る間に近くで食事がしたい、そうするとお店の人が視覚に障害のある方にどうやって案内したらいいのか学んでくださったこともありました。
映画館がオープンしてから商店街の会長さんに呼び止められて、障害者っていっても自分達も年寄りだし、いつ目が見えなくなったり、耳が聞こえなくなったりするかわからないから、自分ごとと思って、どんなことをお店として準備したらいいか、どんな案内をすればいいか教わりたいと声をかけてくれました。
商店街の入口のお店の方からも、信号を待っている視覚に障害のある人がどうやって渡るのかと思ってずっと見ていたら、周りの気配を感じてちゃんと見えなくても渡っていた、でもちょっと危ないと思ったからおまわりさんに音声ちゃんとつけといてって言っといたからと言われたこともあります。
皆が集まれる場所とか日常的に人が行き交うところ、そういう集まれる場所が一つでもあれば、何かできないかなって自発的に動いてくださる人が多くいることを私もこの街の人たちから教わりました。映画館はそういう街作りで作ったわけではないですが、できてから街の人たちの温かさを知りました。
2020年に向けての取り組みもあると思いますが少し構えすぎかなって思うところもあります。施設でもユニバーサル、バリアフリーを取り入れましょうとなったとき、怪我をさせてはいけない、失礼があってはいけないなど、やってはいけないことの想像から始まりそうならないようにっていう対策をたてていくことが多くあります。
私は完璧に整備されていないからこそ人とのコミュニケーションが生まれていくんじゃないかなと思います。障害者の自立って大切だけど、例えば街が音声や点字ブロックなどで全部整備されていて誰の力も借りず一人で歩ける町になればいいかっていうと、そこに抜けがあるから人の手助けっていうところの役割が発生しますよね。そこのバランスはちゃんととっていったほうがいいと思うんですね。
障害者もこういうツールがあるから一人で出来るってほうりだされてしまったら、人の温もりで支えられてきた人のほんとの心も支えられる機会が減ってくるんじゃないかなと、あまり便利になりすぎるのも良し悪しですね。

- 今後の映画館の目標を教えてください
平塚さん私もこの活動を始めるまでは、公共の場で障害のある方を当たり前のように目にする機会があまりなかったですし初めて会うときは緊張もし、偏見ももっていたと思います。
子どものころから、映画館にきたときに盲導犬ユーザーが普通に映画を見てるっていう状況を当たり前のように目にしていれば、見えない人は何もできないって思わないし、見えない人だって映画を楽しんでいる、生活している中で当たり前のように触れ合っていれば、ベースの中にいろんな人が混じっていて、いろんな人が楽しめる環境があるっていうのを子どもの頃から知っているというのは大きいと思います。
そういう場の一つとして映画館で完全ユニバーサルとしてやっているのはChupkiだけですが、真似して作ってくださったらいいなと思うし、結局インフラが整備されたとしても出て行く目的になる場所がなかったら交通が便利になっても意味がないと思うので、色んな人が安心して楽しめる場所が様々な分野で広がっていければいいなと思っています。
少しでもこの映画館がそのヒントになったりモデルになればいいなと思っています。

【CINEMA Chupki TABATA】(シネマ・チュプキ・タバタ)
http://chupki.jpn.org/(外部リンク)
JR山手線「田端駅」北口から徒歩5分
〒114-0013 北区東田端2-8-4 地図(外部リンク)
TEL & FAX 03-6240-8480
障害のある方とのコミュニケーションを深めるサービス介助士
サービス介助士とは、高齢な人や障がいがある人を手伝うときの「おもてなしの心」と「介助技術」を学び、相手に安心していただきながらお手伝いができる人を育成するための資格です。視覚に障害のある方へのご案内やお手伝いを学んでより良いコミュニケーションをできるようにしてみたいという方にもサービス介助士の学びが活かされます。
リベル・ケアフィット 〜「気づき」が集う場所〜
-
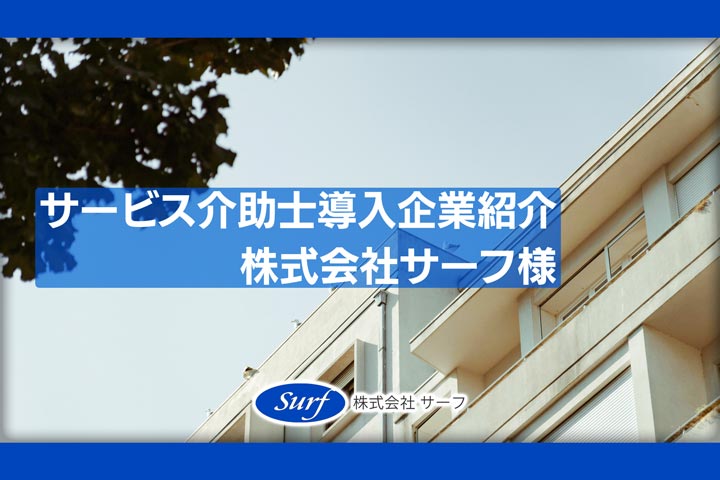
サービス介助士導入企業紹介:株式会社サーフ様
掲載日:
10年以上にわたってサービス介助士の資格取得を継続いただいている株式会社サーフ様。マンション等の大規模修繕事業を展開される同社が、なぜサービス介助士の資格取得を重視されているのか。古川文仁社長にお話を伺いました。
-

「人にしかできないサービス」を追求する——紀ノ國屋が取り組むホスピタリティ
掲載日:
「食を豊かに、人生を豊かに」という理念を掲げる株式会社紀ノ國屋様。1953年には日本初のセルフサービス方式スーパーを開業するなど、流通・小売りの革新を重ねてきました。その長い歴史の中で多くのファンを獲得し、誰もが安心して買い物ができる空間づくりを目指してサービス介助士の資格取得を推進いただいています。紀ノ国屋様のお取り組みについて、インタビューさせていただき、記事にさせていただきました。
-

日本の高齢者人口3,619万人! - 超高齢社会と認知症の推移(2025年版) -
掲載日:
毎年敬老の日に合わせて総務省統計局から発表される日本の高齢者人口。令和7年9月15日付の総務省からの発表によると2025年9月現在の高齢者人口は3,619万人、高齢者人口率は29.4%となりました。超高齢社会が進むと切り離すことのできないテーマが認知症です。これからも社会の高齢化が進行するとどのようなことが起こりえるのか、高齢者に関する様々なデータを見ながら考えていきましょう。