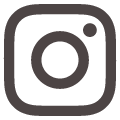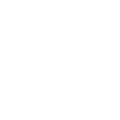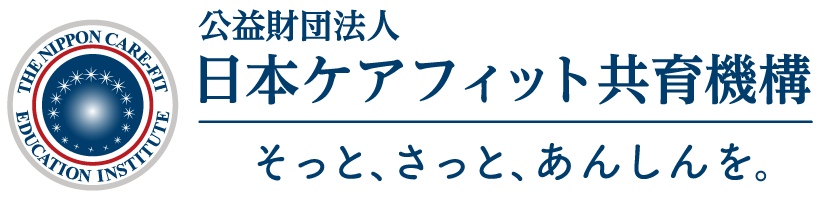東京ディズニーリゾートで活用されるサービス介助の学び
掲載日:

株式会社 オリエンタルランド

CS推進部 CSコミュニケーショングループ
バリアフリープロデューサー
野口 浩一さん

CS推進部 CSコミュニケーショングループ
シニアリーディングスタッフ
長嶋 香奈さん
日本ケアフィット共育機構が発行するフリーペーパー『紲』。
本誌vol.20では、東京ディズニーリゾートの運営を行なっているオリエンタルランドの野口さんと長嶋さんに話しをお聞きしました。
WEBでは、オリエンタルランドで導入していただいているサービス介助の学びについて、また、クオリティの高いホスピタリティを誇るディズニーテーマパークのキャスト文化を支える“褒め合う制度”をご紹介します。
多様なゲストとの基本的な接し方を学ぶために2008年から導入
ーーサービス介助の学びを導入された経緯を教えてください。
野口さん2008年頃から導入を開始したのですが、その当時は、駅や商業施設などのバリアフリーが進み、障害のある方々が外に出やすい環境が整うに連れて、パークに来園されるゲストのなかに、障害のある方が増えてきた時期でした。また、当時も今も、日本では、子どもの頃に障害のある方と机を並べて学んだり運動会で一緒にかけっこをしたりする経験がほとんど得られません。さらに、核家族化が進み、高齢の方と接する機会もあまりありません。そこで、キャストが障害のある方や高齢の方と接するための基本的な考え方をどう学ぶべきか、という考えのもと、社内で提案して導入が決まりました。


長嶋さんパーク内でも、知識や技術の格差が課題となっていました。例えば、アトラクションの担当をしていると、車いす利用の方をお手伝いする機会は多いのですが、商品担当の場合は、基本的に施設内はバリアフリーなのであまりお手伝いする機会がなく、経験を積むこともできません。ですから、いざ応対するときにどうすればよいのかわからない、といった状況でした。サービス介助の学びを導入することで、障害についての全般的な知識を得ることができるので、さまざまな方への応対方法がわかるという点が非常に大きな実りだったと思います。
自分たちの行動を見直し、パークの外でも活用できる
ーー講習を受けた際の感想をお聞かせください。
長嶋さん実際に障害のある方や高齢の方と同じような環境を体験したことは、私にとって大きな衝撃でした。高齢者疑似体験でゴーグルと手袋、重りをつけて道を歩いたときには、もう辛くて辛くて。人とぶつかって、謝ろうと思っても体が重くて動けない。ようやく振り返ったらその人はもうはるか先まで行ってしまっている、といった具合でした。老化という現象自体は理解しているつもりでしたが、ここまで大変なこととは思いませんでした。それから、車いす体験では、ちょっと動かすだけでこんなにスピード感を感じるのか、段差を越えるだけでこんなに怖いのか、ということを、身をもって知ることができました。子どもの頃に曽祖母の車いすを押して歩いたとき、曽祖母は「ありがとう」と言ってくれましたが、本当は怖かったのかもしれない。それは実体験してみないとわからないことでしたね。
ーーサービス介助の学びは、貴社業務にどのように役立っていますか?
長嶋さん講習を受けたキャストのアンケートでは、こちらから積極的に声かけができるようになった、という感想が多いですね。しかも、パーク内だけではなく、プライベートのときにも声をかけられるようになったという声もよく聞きます。パーク内では自分たちがゲストを迎え入れる役割を担っているので、自信を持ってお手伝いができますが、駅やショッピングモールでは自分もゲストの立場ですから、困っている人を見かけても躊躇してしまいがちだったのが、サービス介助の学びを経験することで、積極的に声をかけられるようになった、ということだと思います。
野口さんもうひとつ、講習では異業種の方と同じ空間で学びますよね。それも大きな価値があると感じました。意見交換をすると、パーク内では当たり前のことが他の業種ではそうではない場合もあるとわかる。この、自分たちのサービスに対して一歩引いた視点を得られる経験は、キャストの意識向上に大いに役立っていると思います。

シャイな国民性の日本で、サービス介助の学びが果たす役割は大きい
ーーサービス介助の学びが広まることの意義について、ご意見をお聞かせください。
野口さん私は約35年間ディズニーテーマパークで勤務し、10年以上パーク内のバリアフリーを担当してきました。その経験から、ノーマライゼーションが社会に浸透するためには、ハード面の改善と、人の考え方の変化が必要だと思っています。どちらが先であるべきかを考えると、私は後者だと思います。電車に乗っているときに困っている人を見かけたらひとこと声をかけるといった行動は、シャイな人の多い日本ではなかなか難しいかもしれません。でも、それ当たり前の世の中にならなければ、本当に意味でノーマライゼーションは根付きません。そのために、サービス介助の学びが果たす役割は大きいのではないでしょうか。


コラム:東京ディズニーリゾートの“褒めて伸ばす”従業員教育
上司の立場にあるものは、常に「ファイブスターカード」というカードを持ち歩いています。自分とは異なる部署やアトラクションの担当であっても、「いいな」と思ったキャストにこれを渡すんです。記念品と交換できたり、特別なプログラムに参加できたりするので、キャストのモチベーションアップに繋がります。
カードを渡すのは、自分のためでもあります。人を褒めるというのは簡単なようで難しいですよ。自分の名前を出して褒めるわけですからね。なぜ自分が今の行動をいいと思ったのか。それを言葉にすることで、自分の行動も見直せる。この褒め合う制度は、東京ディズニーリゾートのホスピタリティを支えるひとつの文化だと思っています。(野口さん)
リベル・ケアフィット 〜「気づき」が集う場所〜
-

サービス介助基礎研修 導入企業紹介(株式会社マイヤ様)
掲載日:
1961年に岩手県大船渡市にて創業されて以来、地域の暮らしに必要不可欠な存在として地域の皆様の健康で豊かな食生活に寄与されている株式会社マイヤ様。
株式会社マイヤ様で2023年より実施させていただいているサービス介助基礎研修について、今年度もマイヤびはんストアオール店、マイヤ赤崎店、マイヤマスト店にて実施をさせていただきました。 -

サービス介助士資格導入企業紹介:株式会社ムジコ・クリエイト様
掲載日:
自動車教習所や各種講習の現場には、年齢や身体状況、経験の違いによって、さまざまな不安や困りごとを抱えたお客様が訪れます。安全に学べる環境を整えることはもちろん、その前提として「安心してその場にいられること」をどう支えていくのか──。今回お話を伺ったのは、株式会社ムジコ・クリエイト様。モータースクール事業に携わる松原様、蝦名様にお話をうかがい、サービス介助士資格を導入した背景や、現場で感じている変化について語っていただきました。
-

【バリアフルレストラン実施事例】株式会社INPEX様
掲載日:
日本ケアフィット共育機構が提供する「バリアフルレストラン」は、“障害の社会モデル”の考えに基づいて、社会の多数派と少数派の立場を“反転”させた世界を体験することで、無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)や社会のつくりに潜む“バリア”を理解する体験型プログラムです。