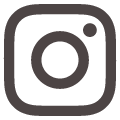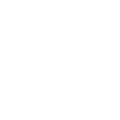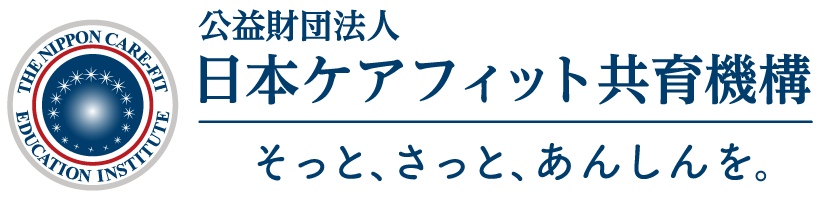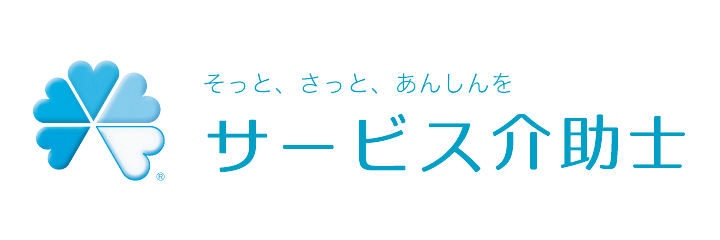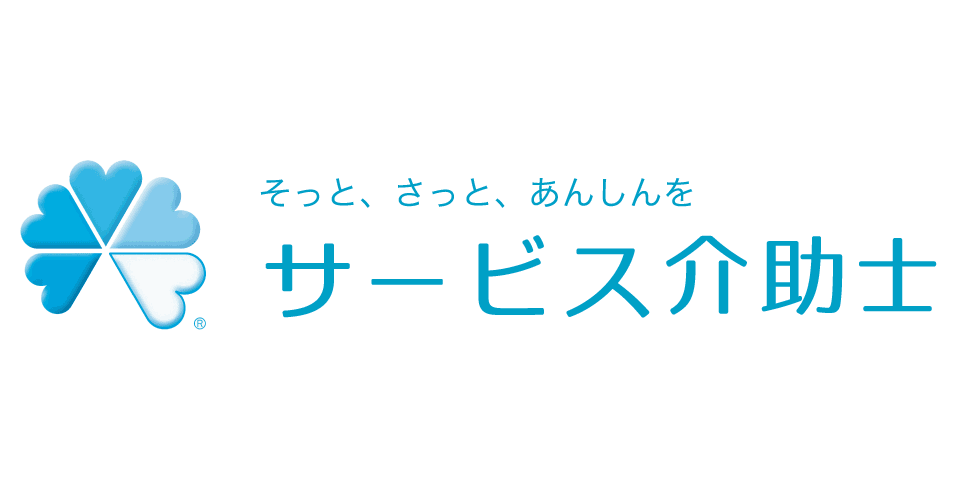
「人にしかできないサービス」を追求する
紀ノ國屋が取り組むホスピタリティ
掲載日:

「食を豊かに、人生を豊かに」という理念を掲げる株式会社紀ノ國屋様。
1953年には日本初のセルフサービス方式スーパーを開業するなど、流通・小売りの革新を重ねてきました。
その長い歴史の中で多くのファンを獲得し、誰もが安心して買い物ができる空間づくりを目指してサービス介助士の資格取得を推進いただいています。紀ノ国屋様のお取り組みについて、インタビューさせていただき、記事にさせていただきました。
株式会社紀ノ國屋 https://www.e-kinokuniya.com/(外部リンク)

経営企画本部 企画部 総務人事グループ
木村 源太 様
ーーサービス介助士資格の導入のきっかけや背景を教えてください。
木村様紀ノ國屋にはご高齢のお客様が多く、また三世代にわたってご利用いただくご家族もいらっしゃいます。そのため、日々の接客の中でお客様への配慮やサポートが自然と求められてきました。
当社にとってホスピタリティとは、お客様のご希望を叶えることそのものです。これまでも店長を中心に、高齢のお客様への対応などを学ぶ機会を設けてきましたが、より体系的で理論に基づいた学びを通して、接遇の質を高めていく必要性を感じていました。
そうした背景のもと、法人として「サービス介助士資格」の取得を進めることになりました。導入当初は対象者を限定していましたが、JR東日本グループの一員となったことを機に、“ヒトを起点としたサービスの創造”というグループ方針と歩調を合わせ、教育体制を再構築しました。2025年度からは新入社員を中心に資格取得を推進し、若手のうちからお客様へのリスペクトと配慮の視点を育てることを目的としています。
ーー紀ノ國屋様の人材育成はサービス介助士の資格取得以外にどのような取り組みをされているのでしょうか?
木村様当社では、入社から2年間を一つの節目として、紀ノ國屋が理想とする人物像に近づけるよう段階的なスキルアップを図っています。
食品小売に関する資格の取得支援はもちろん、タイムマネジメントやホウレンソウなどの実務的スキルに加え、さまざまな人と協働するためのフォロワーシップやリーダーシップも学びます。
当社の経営理念には、「食の提案」と「ホスピタリティ」という二つの柱があります。サービス介助士資格の取得は、そのうちのホスピタリティを理論と実践の両面から学ぶための重要な取り組みです。現場で培われる“おもてなしの心”に理論的裏づけを加えることで、サービス品質をさらに高めていくことを目指しています。
ーー紀ノ國屋様ではホスピタリティの実践において特に大事にされていることは何でしょうか?
木村様私たちがホスピタリティを実践する上で最も大切にしているのは、「お客様への敬意」と「顧客志向の姿勢」です。紀ノ國屋には多様なお客様がいらっしゃいますが、特にスーパーマーケット業態の店舗では、接遇の重要性が一層高まります。
こうした店舗では、商品を購入していただくだけでなく、従業員との会話や店舗で過ごす時間そのものを楽しみにされているお客様も多くいらっしゃいます。中には、「今日も話せてよかった」と言葉をかけてくださるお客様もおり、買い物という行為を超えて、信頼関係を築くことが私たちの使命だと感じています。
そのため、アルバイトやパートの従業員も含め、全スタッフに対して入社時から接遇・ホスピタリティの重要性を丁寧に伝えています。お客様一人ひとりに敬意を持って向き合う姿勢を、職種を問わず全員が共有するよう努めています。
ーーサービス介助士でもホスピタリティ・マインドを学びの核としており、「人」がもたらす価値とは何か?を常に探求しています。特に現在ではAIなどによる自動化・無人化が進んでいます。そのような状況において、人にしかできないこととはどのようなことだと思われますか?

木村様AIは過去のデータを分析し、最適な解を導き出すことに長けていますが、言葉にされない気持ちや、お客様自身も気づいていないご要望をくみ取ることはできません。まさにそこに、ホスピタリティ・マインドの本質があると思っています。
お客様対応で印象に残っているエピソードがあります。ある店舗に、いつもご夫婦で来店されていたお客様がいらっしゃいました。普段は奥様のご要望で、脂身を落としたトンカツ用の豚肉を購入されていたのですが、ある日ご主人様お一人で来店され、「自分は脂身が好きなのに、どうしてここの店は脂を切ってしまうのか」とおっしゃいました。担当者が「奥様がご主人様の健康を気遣われて、いつも脂身を落とすようお願いされていた」とお伝えしたところ、ご主人様は驚かれ、奥様が体調を崩されたことを話してくださいました。その際に奥様と店舗スタッフが、ともにご主人の健康を気づかう姿勢に感謝の言葉をいただきました。
このような気づきや対話の中で生まれる“心の交流”こそ、人だからこそ提供できるサービスと考えております。
ーーそういった対応も人にしかできないサービスで、なかなかできるものではないですね。そのようなホスピタリティの大切さや理念を社員の皆様に伝えていく教育や育成はとても難しいと思いました。
木村様ホスピタリティを伝えることの難しさは、日々実感しています。コロナ禍の影響もあり、人との関わりの中で自己成長を実感する機会が少なかった世代も多く、ゼロから丁寧に教えていく必要があります。
また、近年は「効率よく結果を出したい」「答えを先に知りたい」と考える人も多くなりましたが、接遇には唯一の正解はありません。お客様の満足は常に変化し、経験を重ねて初めて理解できるものです。自ら考え、感じ、行動しながら学ぶ姿勢を育てていくことが大切だと思っています。
当社は路面店やエキナカ店舗など、立地や業態が異なる店舗を数多く展開しており、求められる接客スタイルも多様です。すべての従業員に理念を浸透させるため、社内掲示板や冊子での共有に加え、現場でのコミュニケーションを重視しています。
部門に関わらず本社の人間も、各店舗を訪問した際には従業員と直接話すことで、現場の課題や気づきを把握しています。関西エリアのスタッフとも定期的に面談を行うなど、距離を越えて現場とつながることを大切にしています。
ーー最後に、紀ノ國屋様の今後の取組みや、木村様と同じように人材育成を担っている人たちへのメッセージをお願いします。
木村様今後もサービス介助士の資格を活かしながら、お客様に対するより深い配慮と、心に残るサービスの実現を目指してまいります。ホスピタリティで最も大切なのは、お客様の立場に立って考えること、そして期待を超える”感動“をお届けすることだと考えています。
食品スーパーマーケットという業態は、お客様の健康や生活の一部を支える存在です。食を通じて豊かな時間を提供し、笑顔と幸福をお届けすることが私たちの理想とするサイクルです。
当社の経営理念である「食を豊かに、人生を豊かに」は、時代を超えて共感できる普遍的なテーマです。サービス介助士の導入に取り組む企業の皆様も、この理念を共有する仲間であり、こうした志が広がっていくことで、日本のホスピタリティ文化そのものが世界から見ても誇れる魅力になると信じています。
ーーサービス介助士の皆様で実現けるよう、私たちも取り組みを進めてまいります。ありがとうございました。
木村様日々の接遇の中で、紀ノ國屋様が大切にされているのが「お客様一人ひとりへのリスペクト」。その姿勢をより体系的に学び、確かなホスピタリティとして根づかせるため、サービス介助士の資格取得を推進いただいております。サービス介助士は、単なる接遇のスキル習得にとどまらず、「人が人を想うサービス」を組織の未来につなぐための学びの場となっています。
リベル・ケアフィット 〜「気づき」が集う場所〜
-

サービス介助基礎研修 導入企業紹介(株式会社マイヤ様)
掲載日:
1961年に岩手県大船渡市にて創業されて以来、地域の暮らしに必要不可欠な存在として地域の皆様の健康で豊かな食生活に寄与されている株式会社マイヤ様。
株式会社マイヤ様で2023年より実施させていただいているサービス介助基礎研修について、今年度もマイヤびはんストアオール店、マイヤ赤崎店、マイヤマスト店にて実施をさせていただきました。 -

サービス介助士資格導入企業紹介:株式会社ムジコ・クリエイト様
掲載日:
自動車教習所や各種講習の現場には、年齢や身体状況、経験の違いによって、さまざまな不安や困りごとを抱えたお客様が訪れます。安全に学べる環境を整えることはもちろん、その前提として「安心してその場にいられること」をどう支えていくのか──。今回お話を伺ったのは、株式会社ムジコ・クリエイト様。モータースクール事業に携わる松原様、蝦名様にお話をうかがい、サービス介助士資格を導入した背景や、現場で感じている変化について語っていただきました。
-

【バリアフルレストラン実施事例】株式会社INPEX様
掲載日:
日本ケアフィット共育機構が提供する「バリアフルレストラン」は、“障害の社会モデル”の考えに基づいて、社会の多数派と少数派の立場を“反転”させた世界を体験することで、無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)や社会のつくりに潜む“バリア”を理解する体験型プログラムです。