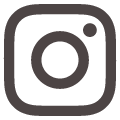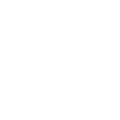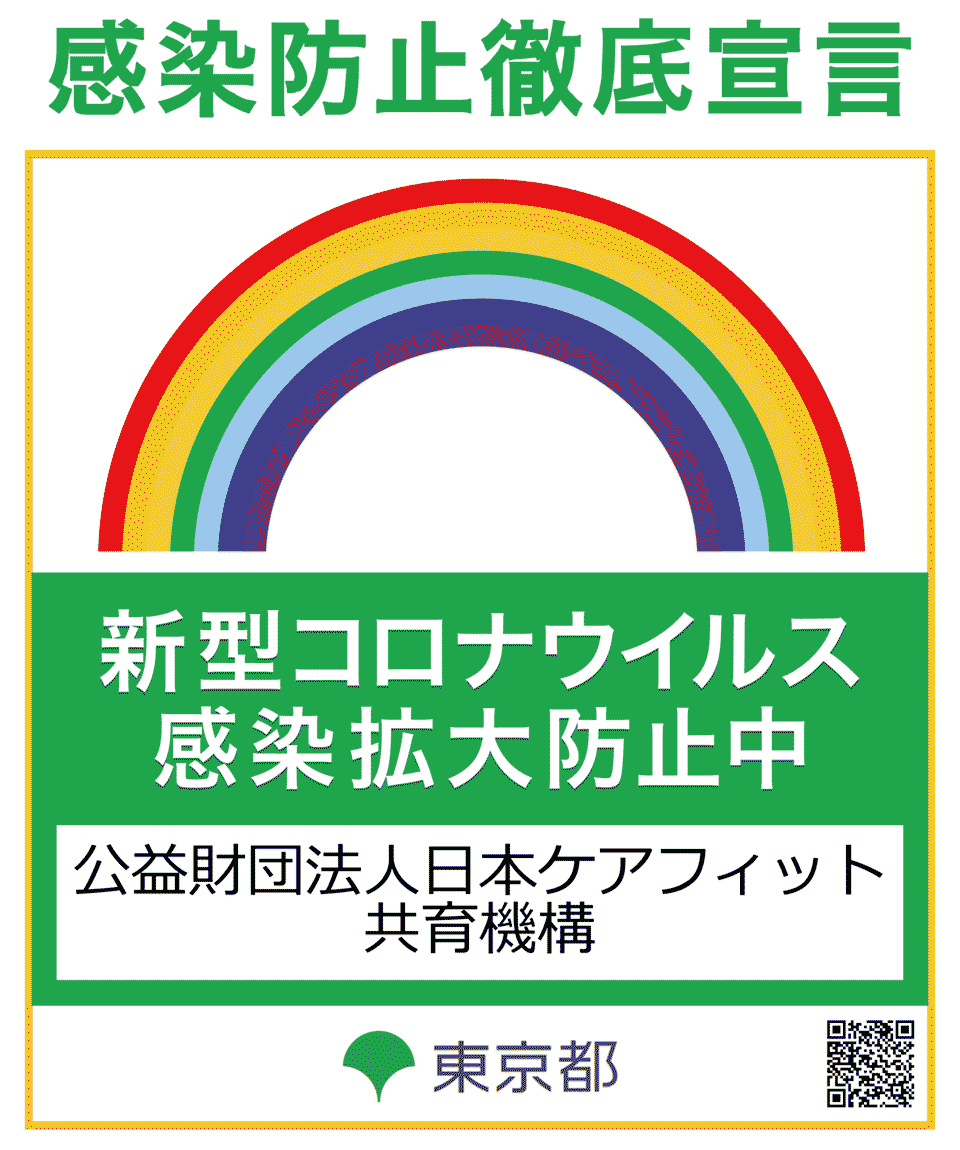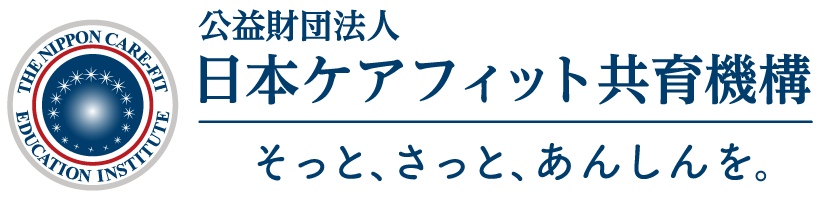アーカイブ
-

掲載日:
サービス介助基礎研修 導入事例(株式会社スペースサービス様)
JAXA筑波宇宙センター内にて、株式会社スペースサービス様ご所属の皆さまに、サービス介助基礎研修をご受講いただきました。
-

掲載日:
サービス介助士 導入企業紹介(株式会社東光ストア様)
北海道・札幌を中心に展開する東光ストアは、創業から半世紀以上の歴史を誇り、スタッフ一人ひとりが「おもてなしの心」を大切にしています。特に、高齢者や障害者への対応には定評があり、積極的に「サービス介助士」を活用することで、従業員の活性化とサービス品質の向上を実現しています。その秘訣についてご紹介します。
-

掲載日:
バリアフルレストランin三菱商事株式会社様
三菱商事株式会社様が、12月9〜13日の5日間、「MC DE&I WEEK 2024」の取り組みの一環として「バリアフルレストラン」の体験イベントを開催しました。企業の体験イベントとしては最長期間の開催となり、多くの社員の皆さまにご参加いただきました。
-

掲載日:
西日本初開催!バリアフルレストランinくまもと
2024年10月14日(月・祝)と15日(火)、熊本城ホール2階エントランスロビーにて、熊本市様主催の市民向けプログラムとして「バリアフルレストランinくまもと」が開催しました。西日本初開催となった今回は、多くの市民が参加し、障害の社会モデルを体験するプログラムに真剣に取り組んでいただきました。
-

掲載日:
公共交通機関等におけるシームレスな移動支援の実現に向けた 参加型バリアフリー教室&ボッチャ体験会 開催レポート
11月23日に武蔵小杉駅前のこすぎコアパークで実施した「みえるバリアフリー教室&ボッチャ体験会」を開催しました。このイベントは、国土交通省の「心のバリアフリー推進のためのモデル検討調査事業」の一環として開催されました(共催:川崎市 協力:東急電鉄株式会社、株式会社東急ストア)。
-
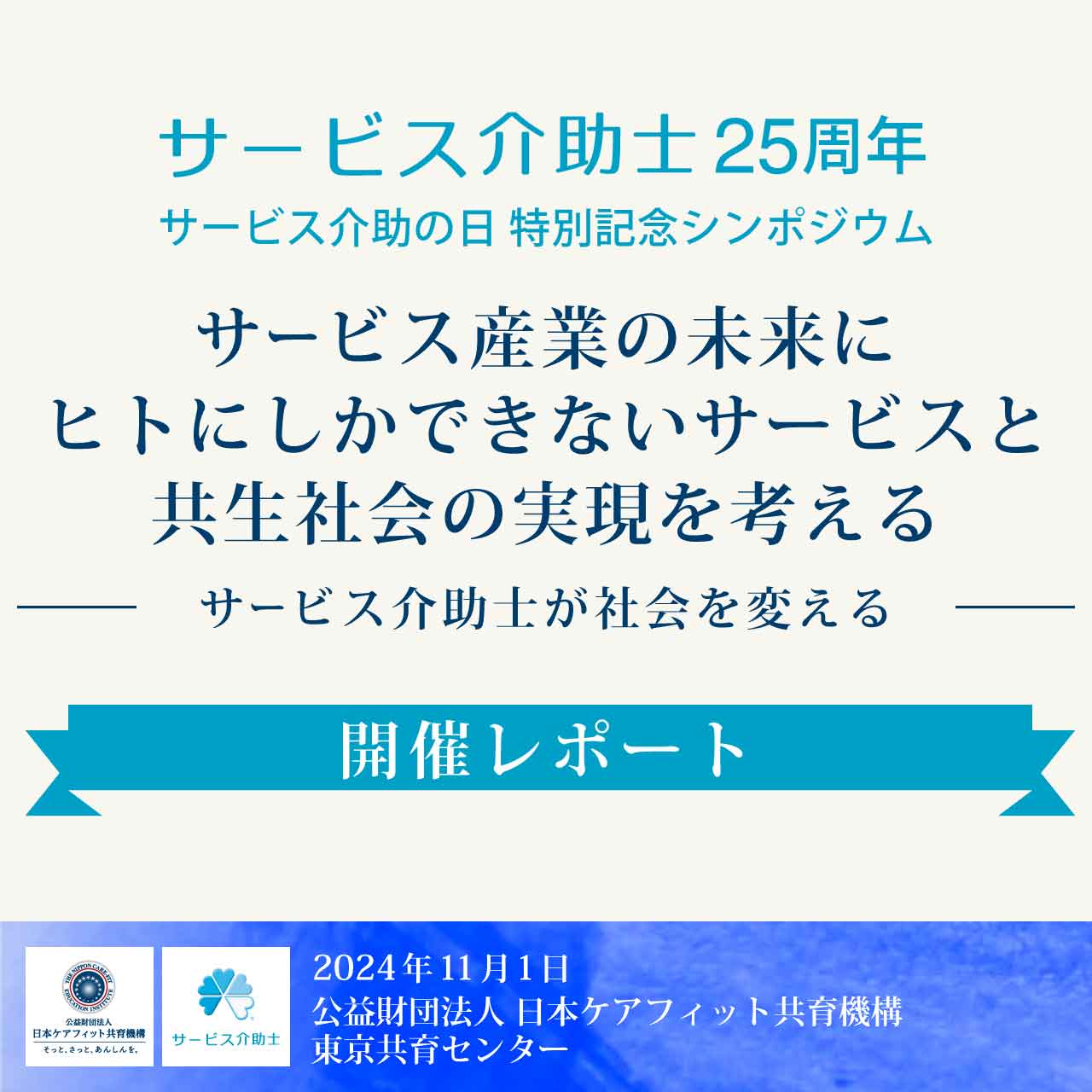
掲載日:
サービス介助士25周年 サービス介助の日特別記念シンポジウム 開催レポート
11月1日は「サービス介助の日」。そしてサービス介助士は開講25年を迎え、これを記念した特別シンポジウム「サービス産業の未来にヒトにしかできないサービスと共生社会の実現を考える〜サービス介助士が社会を変える#x301C;」を開催しました。株式会社オリエンタルランド様、日本航空株式会社様、淑徳大学様からゲストをお呼びし、DX進展や無人化が進む現代において、対人サービスの価値や共生社会の実現について議論が行われました。本記事はシンポジウムの様子をお伝えする開催レポートです。
-

掲載日:
ケアフィットファーム研修 導入事例(NTTアドバンステクノロジ様)
ケアフィットファームでは、ダイバーシティ&インクルージョンを体感できる企業研修プログラムを提供しています。今回はNTTアドバンステクノロジ株式会社様が参加されました。
-

掲載日:
日本の高齢者人口3,625万人! - 超高齢社会と認知症の推移(2024年版) -
毎年敬老の日に合わせて総務省統計局から発表される日本の高齢者人口。最新の発表によると2024年9月現在の高齢者人口は3,625万人、高齢者人口率は29.3%となりました。超高齢社会が進むと切り離すことのできないテーマが認知症です。これからも社会の高齢化が進行するとどのようなことが起こりえるのか、高齢者に関する様々なデータを見ながら考えていきましょう。
-

掲載日:
南海トラフ地震と障害のある人への防災対策:防災介助士の視点で解説
南海トラフ地震は、今後30年以内に70〜80%の確率で発生すると予測されています。この巨大地震に備えて、特に障害のある方々とその家族、そして企業は十分な準備が必要です。本記事では、防災介助士の視点から、障害のある人のための具体的な対策について解説します。
-

掲載日:
バリアフルレストランinアサヒグループホールディングス株式会社 様
アサヒグループホールディングス株式会社様でDE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)を考えるイベントとして初めて開催される「DE&I DAY」にてバリアフルレストランを実施しました。これまで市民向けや学校での開催がメインだったバリアフルレストランを企業様での取り組みの一環に取り入れていただき、DE&I推進にも欠かせない“障害の社会モデル”を体感できるプログラムを提供しました。
-
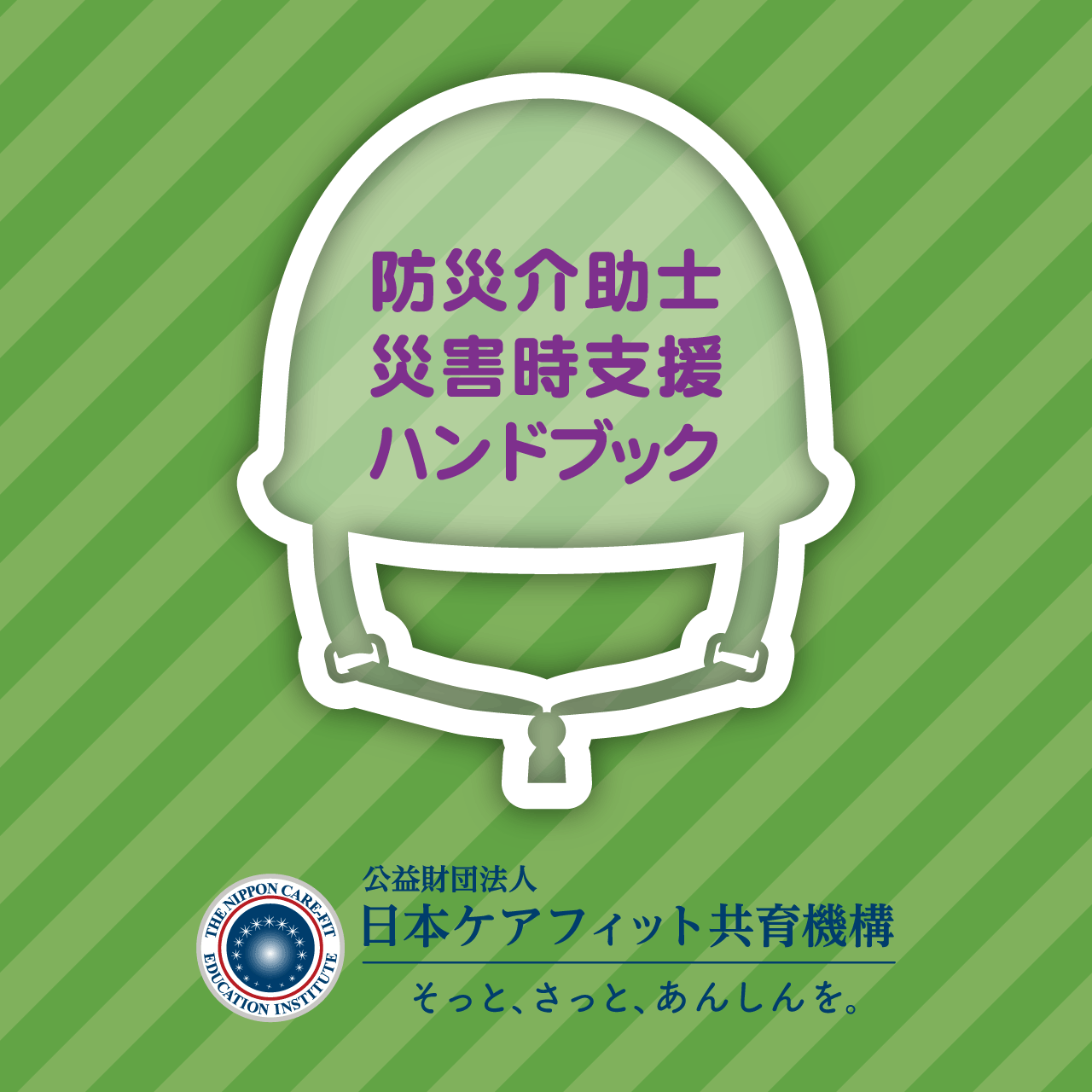
防災介助士 災害時支援ハンドブック
掲載日:(再掲載)
資格取得者に配布している「防災介助士 災害時支援ハンドブック」を一般公開いたします。